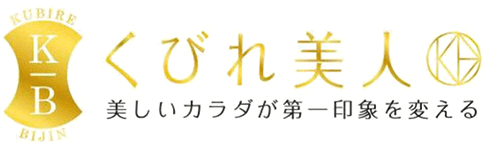体幹の機能を最大限に活かすために知っておきたい可動域

大久保です。
皆さんは、カラダの柔軟性をしっかりと確保できているでしょうか?
カラダの柔軟性と言うと、恐らく多くの方が、“前屈”や“開脚”のイメージを持たれるかと思います。
しかし、実際は全身あらゆる所で、それぞれに適した可動域を確保する必要があります。
それには、柔軟性が高い方が良いところもありますが、反対に、本来あまり可動すべきでないところもあります。
今回のブログは、この柔軟性に関して、人間のコアである脊柱の可動域を書いていきます。
目次
脊柱(背骨)のそれぞれの可動域
それでは背骨の可動域を、部分別に分けて紹介していきます!
頚椎(首)
前屈→60°
後屈→50°
側屈→40°
回旋→45°
頚椎は背骨の中でも、最も可動域範囲の大きな部位です。
日常生活でも視野を確保するために、より大きく動くように出来ています。
胸椎(背中)
前屈→40°
後屈→25°
側屈→25°
回旋→30°
胸椎は胸郭を構成する部位の背骨で、柔軟性が最も低下しやすい部位です。
腰椎(腰)
前屈→50°
後屈→15°
側屈→20°
回旋→10°
腰椎は過活動(とくに回旋)によって、最も違和感を感じやすい部位です。
柔軟性バランスの乱れによる不調
ここまで書いたように、それぞれの部位によって可動域に差があることが分かると思います。
例えば、胸椎の可動域は、臓器を骨で守る構造の一部であることから、大きく動かす機会が少なく、多くの方が確保できていない事が多いです。
胸椎回旋可動域の低下は、代償で本来動かすのが苦手とされる腰椎の過活動を引き起こし、腰部の違和感を引き起こしてしまう可能性が考えられます。
また、腰椎の伸展(後屈)可動域も狭いですので、反り腰の方は、腰椎への負担が高いことも考えられますね。
また今回は詳しく触れていませんが、股関節の可動制限も、代償で腰椎の可動を生み出すため、負担を高めてしまいます。
いずれにせよ、不調を引き起こさないためには、背骨のそれぞれの可動範囲を考慮して、自身のウィークポイントを改善していく必要があるのです。
最後に
今回は背骨の可動域について書きました。
とくに胸椎の回旋可動域低下は、多くの方に見受けられるポイントですので、エクササイズでの改善は大切だなーと、トレーナーとしていつも実感しています。

くびれ美人マネージャー
大久保亮介
高校サッカーでの怪我をきっかけに、プレーヤーではなくトレーナーとなることを決意。
専門学校でトレーナーの基礎知識を習得後、山口県のSSSスポーツプラザ、全国大手の東急スポーツオアシスで活動。
2013年5月にくびれ美人でパーソナルトレーナーとしてデビュー。
2015年7月よりフリーのパーソナルトレーナーとして独立。
2016年4月㈱HATA立ち上げとともにくびれ美人マネージャー兼パーソナルトレーナーとして活動。
2019年7月現在、月200時間以上のパーソナルトレーニングを担当。
【体験料金】
6,600円/60分
(トレーニング55分+カウンセリング5分)
【パーソナルトレーニングの流れ】
①身体の評価
②歪み改善(B.Bトレーニング)
③インナーマッスルトレーニング
④アウターマッスルトレーニング
⑤ストレッチ&マッサージ